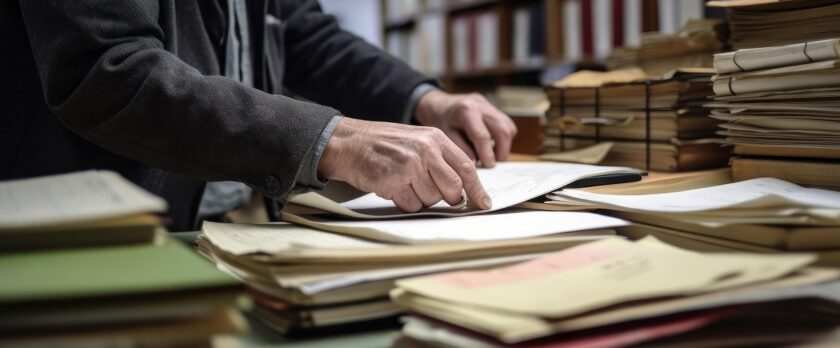はじめに
近年、「死後事務委任契約」という言葉を耳にする機会が増えています。少子高齢化や核家族化が進み、頼れる家族や親族がいない方、または家族に負担をかけたくない方が増えていることが背景にあります。では、死後事務委任契約とはどのような契約で、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。この記事では、行政書士の視点から、契約の概要とともに、その利点と注意点をわかりやすく解説します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる各種手続き(葬儀や火葬、納骨、遺品整理、住居の明渡し、行政手続き、ペットの世話など)を、信頼できる第三者に生前のうちに依頼しておく契約です。契約書は公正証書で作成することが推奨されており、公証人が作成することで、死後に契約が認められないリスクを低減できます。
死後事務委任契約の主なメリット
- 自分の希望通りの死後事務が実現できる
葬儀の形式や納骨方法、遺品整理の方法など、細かい希望を事前に決めておくことで、亡くなった後もご自身の意思が反映されやすくなります。 - 家族や親族の負担軽減
死後の手続きは多岐にわたります。家族や親族がいない場合はもちろん、いても高齢や遠方などで負担が大きい場合、第三者に依頼することで精神的・時間的な負担を大きく減らせます。 - おひとりさまや家族と疎遠な方も安心
近年増加している「おひとりさま」や、家族と疎遠な方でも、死後の手続きを確実に行ってもらうことができます。 - 遺言ではカバーできない事務的な手続きも依頼できる
遺言書では法的効力が及ばない葬儀の希望やペットの世話、SNSアカウントの削除なども、死後事務委任契約なら具体的に依頼できます。 - 専門家に依頼することで安心感が得られる
行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に依頼すれば、法律や手続き面でも安心して任せることができます。
死後事務委任契約のデメリット・注意点
- 相続や財産分与には使えない
死後事務委任契約で依頼できるのは、葬儀や遺品整理などの事務手続きに限られます。相続人の指定や遺産分割、銀行口座の解約などの相続手続きは依頼できません。これらは遺言書で行う必要があります。 - 一部の手続きは法定代理人でないとできない場合がある
たとえば死亡届や年金受給者死亡届の提出は、法律で提出者が限定されているため、死後事務委任契約だけでは完結しないことがあります。相続人や家族との調整が必要になる場合もあります。 - 費用の準備が必要
死後事務の実行には費用がかかります。生前に預託金を用意しておかないと、受任者が立て替えるか、相続人に請求する必要が生じ、トラブルの原因になることがあります。 - 契約内容が不明確だとトラブルのもとに
死後事務委任契約は口頭でも成立しますが、死後に効力を発揮する契約なので、必ず書面(できれば公正証書)で明確に内容を定めておくことが重要です。 - 報酬や費用の支払い時期に注意
報酬や費用の支払い方法・時期を契約で明確にしておかないと、受任者が業務終了まで報酬を受け取れないなどの問題が生じることがあります。
事例紹介
例えば、70代の一人暮らしの女性Aさんは、親族と疎遠で頼れる人がいませんでした。Aさんは生前に行政書士と死後事務委任契約を結び、葬儀や納骨、住居の明渡し、遺品整理などを細かく指定。亡くなった後も希望通りの葬儀が行われ、住居の退去や遺品整理もスムーズに進みました。Aさんのように、家族に負担をかけたくない方や、おひとりさまにとって、死後事務委任契約は大きな安心材料となります。
まとめ
死後事務委任契約は、ご自身の死後に発生するさまざまな手続きを、信頼できる第三者に依頼できる安心の仕組みです。家族や親族に頼れない方はもちろん、家族に負担をかけたくない方にも有効です。一方で、相続手続きには使えないことや、費用・手続きの明確化など注意点もあります。契約内容や受任者の選定、費用の準備など、専門家とよく相談しながら進めることをおすすめします。