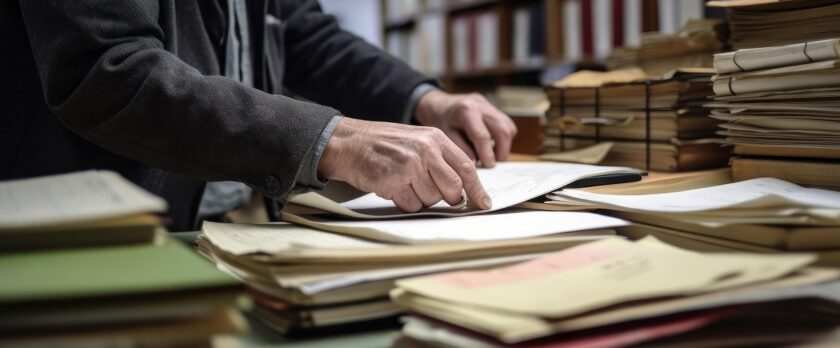はじめに
近年、「死後事務委任契約」に関心を持つ方が増えています。おひとりさまや家族に負担をかけたくない方、親族と疎遠な方など、「自分が亡くなった後の手続きが心配」「葬儀や遺品整理を誰に頼めばいいか分からない」といった不安を抱える方が多くなっているためです。本記事では、死後事務委任契約の作成手順や必要書類について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に発生する各種手続きを、信頼できる第三者や専門家に依頼する生前契約です。葬儀や火葬・埋葬、住居の明渡し、遺品整理、行政手続き、公共料金の解約、ペットの世話、デジタル遺品の整理など、幅広い事務を委任できます。
なお、相続手続き(遺産分割や銀行口座の解約など)は死後事務委任契約の範囲外となるため、遺言書と併用するケースが一般的です。
死後事務委任契約の作成手順
1. 委任する内容を整理する
まずは、ご自身が亡くなった後にどのような事務をお願いしたいかをリストアップします。例えば、葬儀の形式や埋葬方法、遺品整理、行政手続きの範囲、ペットの引き取り先、SNSアカウントの削除など、希望を具体的に整理しましょう。
2. 受任者(依頼先)を決める
受任者は信頼できる親族・知人、もしくは行政書士や司法書士などの専門家、社会福祉協議会や民間企業などから選びます。内容によっては、専門家に依頼することで確実な執行が期待できます。
3. 委任内容・費用を受任者と確認する
希望する委任内容や必要な費用について、受任者と十分に話し合いましょう。費用の目安や預託金の額も確認し、トラブル防止のために明確にしておくことが大切です。
4. 必要書類の準備
契約書作成にあたり、以下の書類を準備します。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 印鑑登録証明書
- 実印(契約書に押印)
- 受任者の本人確認書類
- 戸籍謄本(親族状況の確認が必要な場合)
- 委任内容のリストや希望事項をまとめたメモ
- 預託金の用意(葬儀費用等の前払いが必要な場合)
5. 契約書の作成と締結
契約書は、専門家に依頼する場合は行政書士や司法書士が作成します。親族や知人に依頼する場合でも、トラブル防止のため書面での作成を強くおすすめします。より確実に執行されるよう、公証人役場で「公正証書」として作成する方法が一般的です。
6. 保管・関係者への周知
契約書の正本や謄本は、委任者・受任者がそれぞれ保管します。また、必要に応じて親族や関係者にも契約内容を伝えておくと、死後のトラブル防止につながります。
死後事務委任契約の必要書類まとめ
| 書類名 | 用途・備考 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 委任者・受任者の本人確認 |
| 印鑑登録証明書 | 実印の証明 |
| 実印 | 契約書への押印 |
| 戸籍謄本 | 親族状況の確認(必要な場合) |
| 委任内容リスト | 希望する事務内容の整理 |
| 預託金 | 葬儀費用等の前払いが必要な場合 |
※公正証書作成の場合は、公証役場で追加書類が必要な場合があります。事前に公証役場や専門家に確認しましょう。
事例紹介
長年一人暮らしをしていたBさん(70代・女性)は、親族と疎遠で自分の死後の手続きに不安を感じていました。Bさんは行政書士に相談し、葬儀や住居の明渡し、公共料金の解約、遺品整理、ペットの引き取りなどを死後事務委任契約で依頼。契約時に必要書類を揃え、公正証書で契約を作成したことで、安心して日々を過ごせるようになりました。
まとめ
- 死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを第三者に依頼できる生前契約です。
- 委任内容の整理、受任者選定、必要書類の準備、契約書作成という流れで手続きを進めます。
- 書面での契約、公正証書化、関係者への周知がトラブル防止のポイントです。
- 必要書類は本人確認書類、印鑑登録証明書、実印、戸籍謄本、委任内容リストなどです。
- 詳細や不明点は、行政書士などの専門家や公証役場に相談しましょう。