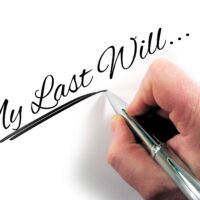はじめに
遺言書を作成する際、遺言内容を確実に実現するためには「遺言執行者」を選任することが重要です。遺言執行者は、被相続人の意思を尊重し、遺言内容を正確かつ円滑に執行する役割を担います。本記事では、遺言執行者を選ぶ際のポイントと注意点について解説します。
遺言執行者とは?その役割と必要性
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するための手続きや管理業務を行う人のことです。具体的には以下のような業務があります。
- 相続財産の調査と目録作成
- 不動産や預貯金などの名義変更手続き
- 遺贈(特定の人へ財産を渡す)の実施
- 遺言内容に基づく相続手続き全般
特に、遺言で「認知」や「推定相続人の廃除」を記載する場合は、法律上、遺言執行者が必要です。
遺言執行者を選ぶ際のポイント
- 信頼できる人物であること
遺言執行者には高い倫理観と責任感が求められます。相続人間でトラブルが起こりそうな場合は、中立性が求められる第三者(弁護士や行政書士など)を選ぶことも検討しましょう。 - 法律上の資格要件を満たしているか
民法では未成年者や破産者は遺言執行者になれないと定められています(民法第1009条)。 - 専門知識の有無
遺産には不動産や株式など複雑な資産が含まれることがあります。これらの処理には専門知識が必要なため、専門家を選任すると安心です。 - 複数人または代替案の指定
遺言執行者が一人ではなく複数人を指定したり、代替案として別の候補者も記載しておくことで、万が一の場合にも対応できます。
注意点
- 就任拒否や辞退への対応
指定された人物が就任を拒否したり辞退する可能性があります。この場合、家庭裁判所に申し立てて新たな遺言執行者を選任してもらう必要があります。 - 報酬について明記する
遺言執行者には報酬が発生する場合があります。相続財産から支払うことになるため、その旨を遺言書に明記しておくとトラブル防止につながります。 - 相続人との関係性
選任した人物が相続人と対立関係にある場合、円滑な手続きを妨げる可能性があります。そのため、中立性を重視して選ぶことが重要です。
事例:信頼できる第三者への依頼
例えば、高齢のAさんが自分の財産を息子Bさんと娘Cさんに分ける内容で遺言書を作成しました。しかし、BさんとCさんは過去に相続争いになった経緯がありました。このような場合、Aさんは中立的な第三者である行政書士Dさんを遺言執行者として指定しました。これにより、Aさん亡き後もスムーズに手続きが進みました。このように第三者への依頼は有効な選択肢です。
まとめ
遺言執行者は、被相続人の意思を実現する重要な役割を担います。そのため、信頼性、中立性、専門知識などを考慮して慎重に選ぶことが大切です。また、不測の事態にも対応できるよう代替案や報酬についても明記しておくと安心です。行政書士や弁護士など専門家への相談も積極的に活用しましょう。