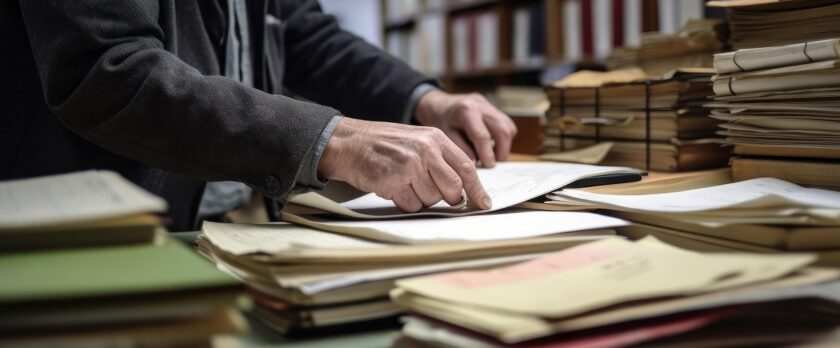はじめに
近年、身寄りのない方や単身世帯の増加を背景に、「死後事務委任契約」の重要性が高まっています。死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生するさまざまな手続きを、信頼できる第三者に事前に委任しておく契約です。しかし、せっかく契約を結んでも、内容や手続きに不備があるとトラブルに発展することも少なくありません。本記事では、死後事務委任契約でよく起こるトラブルと、その防止ポイントについて、最新の公的情報に基づき詳しく解説します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、本人が生前に「自分の死後に必要となる事務手続き」を特定の人(受任者)に委任する契約です。主な内容には、葬儀や納骨の手配、行政手続き(死亡届や保険証の返還、年金の抹消など)、遺品整理、デジタル遺品の管理、ペットの引き継ぎなどが含まれます。
この契約を結ぶことで、本人の希望に沿った形で死後の手続きを進められるだけでなく、親族や関係者の負担軽減や、身寄りのない方の「無縁仏」化防止にも役立ちます。
死後事務委任契約でよくあるトラブル
死後事務委任契約は、亡くなった後に効力を発揮するため、事前の準備や契約内容が不十分だと、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
- 親族との対立や反対
- 口頭契約や内容不明瞭による無効化
- 二重契約の発覚
- 受任者が適切に対応しない、または連絡が取れない
- 行政手続きの不備による手続き遅延
トラブルを防ぐためのポイント
1. 必ず書面で契約し、公正証書化する
口頭契約は証拠が残らず、後から「そんな契約はしていない」と主張されるリスクがあります。必ず書面で契約し、できれば公正証書にしておくことで、法的効力が高まりトラブル防止につながります。公正証書は公証役場で作成でき、第三者による証明となるため、親族や関係者からの異議申し立てにも強い証拠となります。
2. 契約内容を具体的に明記する
「葬儀をお願いしたい」「遺品整理を任せたい」といった曖昧な内容ではなく、どのような事務を、どこまで、どのような方法で行うかを具体的に記載しましょう。たとえば「○○寺に納骨する」「SNSアカウントを削除する」など、細かな希望まで盛り込むことが大切です。
3. 受任者は信頼できる相手を慎重に選ぶ
受任者は、親族や友人だけでなく、専門家(行政書士や弁護士、信託会社など)も選択肢となります。受任者が信頼できる人物か、万が一のときに確実に連絡が取れるかをしっかり確認しましょう。また、受任者の変更や複数人での契約も検討できます。
4. 親族や関係者への説明・周知を徹底する
死後事務委任契約を結んだことを、親族や関係者に事前に伝えておくこともトラブル防止の重要なポイントです。突然第三者が死後事務を行うと、親族が反発したり、手続きが進まないケースもあります。契約内容や受任者の連絡先を、信頼できる親族や関係者に共有しておきましょう。
5. 定期的な見直しと契約内容のアップデート
生活環境や希望が変わることもあるため、契約内容は定期的に見直しましょう。受任者が高齢化したり、希望する葬儀方法が変わった場合など、状況に合わせて契約を更新することが大切です。
6. 費用や報酬、支払い方法も明確に
死後事務委任契約にかかる費用や、受任者への報酬、支払い方法も契約書に明記しておきましょう。費用の出所や支払い時期が曖昧だと、受任者が手続きを進められなくなるリスクがあります。
死後事務委任契約の具体的な流れ
- 委任したい内容を整理する
- 信頼できる受任者を選ぶ
- 契約内容・費用・報酬などを明確にし、契約書を作成する
- 公正証書化する(推奨)
- 親族や関係者に契約の存在を伝える
- 定期的に内容を見直す
事例紹介
東京都在住の60代男性Aさんは、身寄りが遠方にしかいないため、信頼できる知人Bさんと死後事務委任契約を締結しました。契約には「葬儀の手配」「行政手続き」「ペットの引き継ぎ」などを具体的に明記し、公正証書で作成。Aさんは契約内容を親族にも説明していたため、亡くなった際もスムーズに手続きが進みました。
まとめ
死後事務委任契約は、本人の希望を実現し、遺された方々の負担を減らす有効な手段です。しかし、契約内容が不明瞭だったり、受任者との認識にズレがあると、かえってトラブルの原因となります。必ず書面で契約し、公正証書化、具体的な内容の明記、信頼できる受任者の選定、親族への周知、定期的な見直しを徹底しましょう。公的ガイドラインや専門家のサポートも活用し、安心できる終活を進めてください。