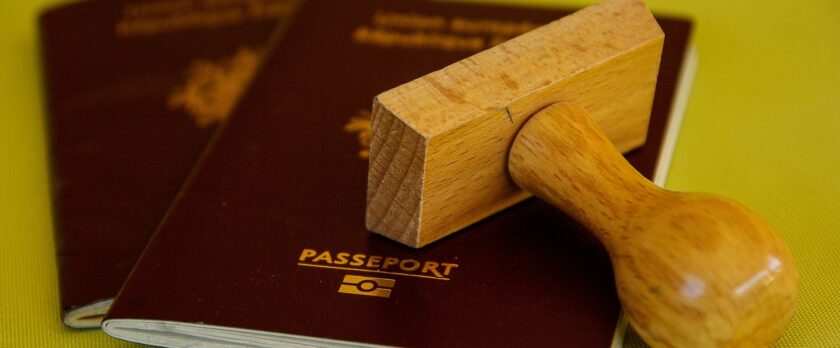はじめに
外国人が日本で働く際に多く利用される在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」は、専門的な知識やスキルを活かして日本企業で就労するための重要なビザです。しかし、申請時によくある悩みが「大学で学んだ専攻と実際に就く仕事内容が完全には一致しない場合、許可が下りるのか?」という点です。この記事では、こうしたケースで不許可を回避するためのポイントを、最新の法務省ガイドラインや実務上の注意点を踏まえて詳しく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、理学・工学などの自然科学系(技術)、法律・経済・社会学などの人文科学系(人文知識)、通訳・翻訳・海外営業などの国際業務の3分野に分かれています。申請者は、これらの分野に関連する学歴や実務経験を有し、かつ日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。
不許可となりやすいケース
このビザ申請で最も重視されるのは「学歴(専攻)や職歴と、実際に従事する業務内容との関連性」です。たとえば、教育学部卒が弁当工場で箱詰め作業に従事する場合、専門性や関連性が認められず不許可となります。また、経営学専攻者がプログラマーとして申請した場合も、関連性が薄いと判断されやすいです。
専攻と仕事内容が異なる場合の許可のポイント
1. 関連性を客観的に説明する
- 専攻と業務の間に直接的な関連がない場合でも、間接的な関連性を明確に説明することが重要です。
- たとえば、経済学部卒で営業職に就く場合、「大学で学んだマーケティングや経済分析の知識を営業戦略の立案や顧客分析に活かす」といった説明が有効です。
- 職務内容説明書や雇用契約書に、学歴で得た知識がどのように業務で活用されるかを具体的に記載しましょう。
- 「自社では関連がある」と思っても、審査官が納得できる客観的な書類作成が不可欠です。
2. 実務経験の活用
- 学歴と業務内容の関連性が弱い場合でも、10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)があれば要件を満たせます。
- 実務経験を証明する書類(在職証明書や職務内容証明書)をしっかり準備しましょう。
3. 業務内容の専門性を強調
- 単純作業や補助的業務は不許可となりやすいため、専門的知識やスキルを要する業務であることを明確に説明します。
- たとえば、営業職でも「データ分析や戦略立案、海外取引先との交渉」など、専門性の高い業務内容を強調しましょう。
4. 実務研修期間の扱い
- 採用当初に実務研修で一時的に専門外の業務に従事する場合でも、日本人新卒社員と同様の研修であり、在留期間全体のごく一部であることを説明できれば、許容される場合があります。
- 研修計画書や雇用契約書に、研修の目的と期間、主な業務内容を明記しましょう。
5. 申請書類の不備や不一致を防ぐ
- 学歴証明書、職務内容説明書、雇用契約書など、提出書類に矛盾や不足がないように注意します。
- 必要に応じて、専門家(行政書士)に相談するのも有効です。
事例
外国の大学で心理学を専攻したAさんが、日本のIT企業で人事職として採用される場合を考えます。心理学の知識は、従業員のメンタルヘルス管理や組織開発、人材育成プログラムの設計など、人事業務に活かせる部分が多くあります。このような関連性を、職務内容説明書や申請理由書で具体的に説明することで、許可の可能性が高まります。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請では、大学の専攻と仕事内容が完全に一致していなくても、関連性を客観的かつ具体的に説明できれば許可される可能性があります。実務経験の活用や、専門性の強調、書類の整合性など、細かなポイントを押さえて申請準備を進めましょう。不安な場合は、行政書士など専門家に相談することもおすすめです。